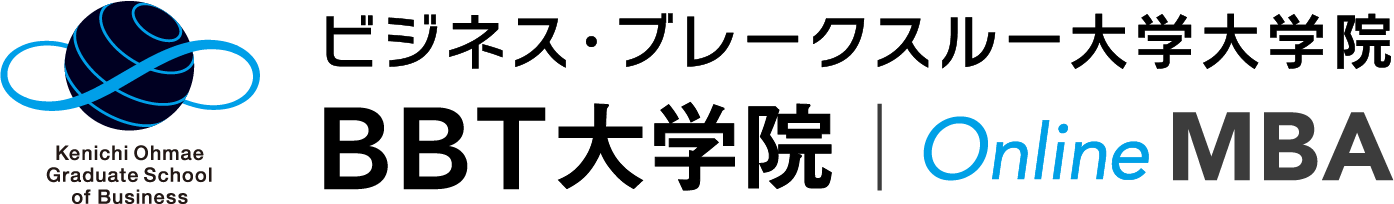オリンピックの大改革を提言
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学名誉教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部

オリンピックイヤーの2020年が幕を開けました。東京に招致することが決定した2013年以来、何かとトラブル続きの準備期間でした。とどめのすったもんだは開催まで1年を切った段階になってからマラソンと競歩の開催地を変更したことでしょう。トラブルの元凶について、IOC(国際オリンピック委員会)が提示する開催条件の無理難題、また、無理難題なのを承知のうえで、嘘八百をならべて立候補する開催都市にあるとBBT大学院・大前研一学長は言います。
大前学長は、オリンピックを開催する時期、開催単位、スポンサーに関する大改革を提言します。
“スポンサーファースト”で決まる開催時期を“アスリートファースト”に見直すべき
2020年のオリンピックの開催期間は「7月15日から8月31日までの16日間」と条件が設定されていた。招致活動を行った東京オリンピック・パラリンピック招致委員会(現在は大会組織委員会および東京都はそれを承知のうえで立候補し、「この時期の天候は晴れる日が多くかつ温暖(mild)であるため、アスリートが最高の状態でパフォーマンスを発揮できる理想的な気候である」と立候補ファイルに嘘を記したのである。イカサマ招致だったから、マラソンと競歩の会場を札幌に移すというIOCの決定に従うほかなかったわけである。
IOCにも問題がある。7~8月は北半球の都市はほとんどどこも猛暑、酷暑に見舞われる。とてもアスリートファーストとは言えない時期が夏季五輪の開催条件に設定される理由は、オリンピックの商業化、つまり、欧米のテレビ局から支払われる巨額の放映権料がIOCの収入の柱になっているからだと言われている。
たとえば、米NBC(全国放送会社)は76億5000万ドルをIOCに支払って、2032年大会までの米国における独占放映権を得ている。米国ではアメリカン・フットボール(NFL)のシーズン開幕やメジャーリーグ(MLB)のプレーオフなどのスポーツイベントが秋に集中し、欧州では人気のサッカーがシーズンを迎える。テレビ局として世界的なスポーツイベントが集中する秋口よりも、イベントが夏枯れする7~8月にオリンピックを開催するほうが視聴率を稼げる。ということで、スポンサーファーストの開催時期になっているのだ。
ところが2019年9月、カタールのドーハで開催された世界陸上の女子マラソンで、真夜中に実施したにも関わらず、高温多湿の環境が選手を苦しめ、参加者の40%超が棄権する事態になった。これを受けてIOCは「マラソンと競歩の開催地を札幌に移転する」と速やかに決定、発表した。
スポンサーファーストで決まる開催条件は改革すべきポイントである。アスリートファーストというなら、夏季五輪は主催国のベストシーズンを選ぶようにしたほうが良い。あるいは時期をずらした分散開催という考え方もある。
オリンピックの開催単位を都市単位ではなく国家単位にすべき
マラソンと競歩の競技会場を札幌に奪われたオリンピック開催都市の東京――。「IOCの決定には同意できないが、決定を妨げないのが東京都の決断」と東京都知事の小池百合子氏は不快感を示した。もし都知事の我が通って、酷暑の東京でマラソンや競歩を開催して、重大事故でも起きたら都知事の政治生命にもかかわる。政治家は予測不能のリスクを負うべきではない。むしろ都知事としてはリスクを軽減できる札幌移転を歓迎すべきところである。
そもそもオリンピックが都市単位で開催されるのは、古代オリンピックが都市国家間で競われたことに由来する。しかし近代オリンピックは国家単位で競うのだから「開催国」ベースのコンセプトに切り替えても良いのではないか。そうすれば競技会場の選定なども含めてオペレーションが非常に楽になる。サッカーやラグビーのワールドカップのように競技する場所を散らして最適地で行うようにすれば、国を挙げて盛り上がることができるだろう。ちなみに2024年の「パリ五輪」ではサーフィン会場が南太平洋上にあるフランス領タヒチに決まった。
オリンピックのスポンサーを見直すべき
スポンサーとの関係を見直す必要もあるだろう。スポンサーを抜本的に入れ替えて、たとえば既存メディアとは一線を画したグーグルやフェイスブック、ネットフリックスのようなグローバル企業にスポンサーになってもらうことを提案したい。中国のBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)などの新興企業も喜んでスポンサーになるであろう(アリババはすでにスポンサー)。
こうした抜本的な改革を日本とJOC(日本オリンピック委員会)は提案していくべきだと思う。東京オリンピック・パラリンピックが終われば、数え切れないくらいの反省点が浮かび上がってくるだろう。それらを総括して、五輪改革につなげる提言を準備すべきである。東京で2度の夏季五輪を開催し、札幌や長野でも冬季五輪を開催した日本だからこそ言える立場でもある。今回の東京オリンピックの経験と反省を今後のオリンピックに以降に生かすことができないとするならば、日本人、そして特に東京都民には、むなしさだけが残ることになる。何の改革もせずに、競技数もコストも肥大化して開催国の負担が増すばかりでは、五輪を開催を開催する魅力が失われていく。
※この記事は、『プレジデント』誌2020年1月31日号pp.78-79を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役会長。ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学名誉教授。